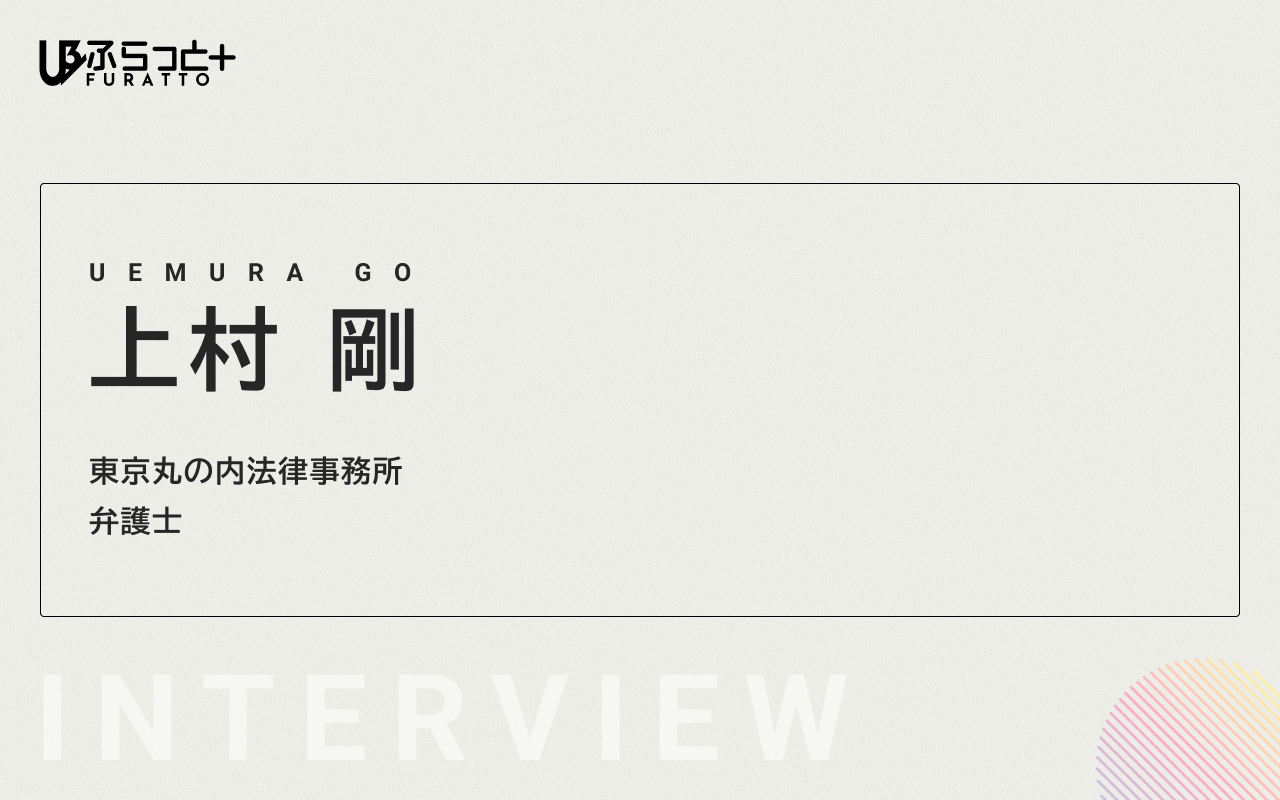
東京丸の内法律事務所【弁護士】上村 剛
会社を「守り、残す」ために──倒産・事業再生に奮闘する弁護士の挑戦
不安定な時代に踏み入れた「企業法務」の世界
—— まずは、弁護士を目指された動機についてお聞かせください。
上村: 私は大阪出身で、大学入学を機に東京に来ました。法学部に進学したものの、当時は「弁護士になろう」という意識は全くなく、むしろ、司法試験を受ける友人を見て「自分には合わない」と思っていました。
就職活動の時期は、山一証券の自主廃業や日本長期信用銀行の破綻などがあり、日本の大企業の在り方が根本的に変わる時期でした。親族にメディア関係者が多かったこともあってか、卒業後はディレクターとしてNHKに入局するのですが、取材テーマとしても経済に関係した内容を選ぶことが多かった記憶です。NHKでは7年間勤務し、災害報道から長尺の番組まで、様々な経験をすることができました。
転機の1つは、2002年にやってきます。電力会社のトラブル隠しなどを契機に、コンプライアンス(法令遵守)という言葉が世に広がり始めたのですが、企業内のコンプライアンス向上に向けた取組みの企画で、大企業の法務部を取材する機会がありました。このときの取材経験を通して、法令違反が企業の存亡に関わる事態につながることを実感しました。同時に、大学のときには避けようとしていた法律の世界が、急に身近に思えてきたのです。ちょうど、法科大学院(ロースクール)の制度がスタートした時期でもあり、職業としての弁護士に興味を持つようになりました。
—— 7年のキャリアを手放す決断は大きかったのでは?
上村: 若かったからこそ挑戦できたのかもしれませんが、NHKの同期や大学の友人などに相談するうちに、弁護士を目指す気持ちが固まっていきました。ただ、ディレクターの仕事も面白くなってきたころで、いろいろ悩んだりしつつ、最終的には2005年4月に退職、翌日から法科大学院に入学、となりました。
未来へつなぐ「事業再生」の奥深さ
—— 弁護士になってからは、どのような仕事を経験されてきましたか?
上村: 弁護士登録後、最初に所属した大規模事務所では、主として金融案件を担当していましたが、法科大学院のときに興味を持った知的財産権についても取扱い分野にしたいと考えていました。どちらかというと、倒産・事業再生は避けていたかもしれません。ところが、ある案件で、破産手続に関わったことが転機になりました。債権者の代理人として出席した債権者集会で、破産管財人の仕事を目の当たりにすることができ、これはやりがいのある仕事ではないか、と直感したのです。
—— そこから現在の「倒産・事業再生」を扱う事務所に移籍されたのですね。
上村: メディアの世界に進んだくらいですから、オフィスにこもっているよりも、現場に出る方が性に合っているように思います。
倒産事件では、会社のオフィスはもちろん、様々な現場に赴きますし、外部からはうかがい知れないような企業の内部を見ることができます。倒産事件は、基本的に会社の清算業務ですので、債権者への配当原資とするべく不動産、自動車、重機などの売却・換価も担当しますし、未払賃金の計算もやります。「倒産」という限れた局面ではありますが、企業の存亡に当事者として関与することができ、大げさにいえば、その企業を「丸抱え」するようなところがあります。当然、扱う法分野も極めて広く、日々研鑽が必要です。ちなみに、私の場合、知的財産が絡む倒産案件も多いです。
限られた時間の中で、多様な問題を解決し、利害関係者間の調整を行い、裁判所と協議し、債権者にも納得してもらえるような「着地」を目指していく一連の流れは、オンエアまでの短い時間で取材し、構成し、ロケして編集……という番組制作のプロセスに一脈通じるところがありまして、個人的には、ディレクターの仕事と親和性があるように感じています。
論理的思考で「関係者全員が納得して終われる」ように
—— お仕事で大切にしている価値観を教えてください。
上村: 私が重視しているのは「関係者全員が納得する」ことです。倒産事件に限りませんが、弁護士が関与するような案件では、多くの場合、利益を受ける人がいる一方で、不利益を被る人もいます。どのような結果になるにしても、また、依頼者にとっても相手方にとっても、納得して案件を終結できることが重要ではないかと思うのです。大きな禍根を残したまま終わるよりは、少しでも前向きになってほしい、という私の願望でもあります。ですので、依頼者の当初の意向と異なる結果となっても、それが納得できるものであれば、それでよいと思うのです。
——冷静な視点を示す役割でもあるのですね。
上村: そうです。メディアの世界では視聴者の「興味を引く」「心をつかむ」ことが番組の入り口として重要でした。これに対して、法律の世界は基本的に終始ロジックです。どのような論理であれば関係者が「納得」できるのか、その探求と表現してもよいかもしれません。メディアの仕事との差異について、よく「右脳と左脳の違い」と説明したりしています。大学時代に所属していたゼミ(法学のセミではありません)に、弁論に優れた友人がおりまして、彼の論理的な思考とプレゼン能力を尊敬していたのですが、「論理の世界」に戻ってきたので、再び彼を見習いたいと思ったりしています。
「残せる倒産」を目指す
—— 今後の展望について教えてください。
上村: これまで、破産事件における破産管財人や申立代理人を多く経験してきましたが、今後は「残す」方向にも力を注ぎたいと思っています。例えば、破産手続を選択するにしても、将来性のある部門については他の企業に譲渡することで、事業の一部は残すことができますし、従業員の雇用も守ることができます。その譲渡代金があれば、債権者に対して、より多くの配当を行うことができるかもしれません。
私は、破産管財人などの裁判所に選任される側と、申立代理人などの企業側の双方を多く経験していますので、倒産事件の手続全体を理解しています。いずれか一方しか経験がないと、手続の流れや展開を読み切れないところが出てくるかもしれませんが、私の場合、その点は強みがあると思っています。
税理士・会計士の先生方が顧問先の経営悪化に直面したとき、きっとお役に立てるはずです。
少しでも迷ったときこそ、相談してほしい
—— 最後に、読者へメッセージをお願いします。
上村: 弁護士には、「困ったとき」の相談先といったイメージがあるかもしれません。しかしながら、本来、法律は「転ばぬ先の杖」だと思いますので、深く悩むような状況になる前に相談していただく方がよい結果となることが多いと思っています。顧問先にちょっとした異変を感じたときが、実はベストな相談タイミングかもしれません。
特に中小企業の場合、普段から弁護士と付き合いのないところも多くあると思いますが、弁護士は敷居が高いと感じてしまうのか、問題が大きくなってから弁護士のところに駆け込む印象があります。時間が経てば経つほど、打てる手が限られてきます。些細なことでも構いませんので、不安を感じたら一度声をかけてもらえると、その先の展開が変わってくるかもしれません。
先生のご紹介
上村 剛 [UEMURA GO]
略歴:弁護士・公認不正検査士。大学卒業後、日本放送協会(NHK)で、ディレクターとして7年間勤務。報道番組の取材中に企業の法務部に興味を持ち、法律の奥深さに触れる。ロースクールを経て弁護士となり、国内有数の法律事務所で金融やM&Aなどを担当後、現在の事務所に移籍、現在は主に企業法務、倒産・事業再生、知的財産を扱う。特に企業の「いい部分」を残し再生させる支援に注力している。
所在地:東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 新東京ビル225区 東京丸の内法律事務所
HP:https://www.tmlo.jp/
